親が施設に入ったあと、自宅をリフォームして住みやすくしたいと思っても「名義や手続きがややこしい」「認知症だと契約できない?」など、不安や疑問を抱えていませんか?
実際に、親が元気なうちにはリフォームの話を切り出しにくく、気づけば手遅れになってしまうケースは少なくありません。私自身も現場で多くの相談を受け、その難しさを目の当たりにしてきました。
本記事では、親が施設に入ったあとにリフォームを進める際に直面する主な課題とリスクについて解説します。
■この記事でわかること
・認知症とリフォーム契約の関係
・贈与とみなされるリスク
・名義や登記にまつわるトラブル
・後見人制度でできること/できないこと
施設に入ったあとでのリフォームは、法律的にも手続き的にも非常にハードルが高いため、親が元気なうちに話し合いと準備をしておくことが何より重要です。
親が施設に入る前にリフォームや住まいの将来像について考える大切さを理解でき、家族で円滑に話し合うきっかけをつかむことができます。
※税務や権利関係のご相談は、資格を持つ税理士や司法書士にご相談ください。
リフォームが難しくなる主な理由
認知症のリスク
施設や支援が必要になる頃は、多くの場合で認知機能の低下が始まっています。
生活環境の変化は認知症の進行を早める可能性があり、さらにリフォーム契約自体も「名義人本人」でなければ成立しません。
つまり、親が認知症を発症してしまうと契約や承諾ができなくなり、リフォーム工事を進められなくなります。
贈与とみなされるリスク
「贈与=親から子へのもの」と思われがちですが、逆もあります。
子供が親名義の家をリフォームするために費用を負担すると、その金額や出費によって資産価値が上が分を「贈与」とみなされるケースがあります。
建物の名義とリフォーム契約者は同一であることが基本です。
親が施設に入り、さらに認知症を発症すると、承認や契約ができず手続きが滞ってしまいます。
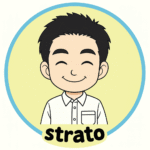
少額の工事だと問題ないありませんが、110万円を超えると注意が必要です。
名義人・登記の問題
古い土地や実家では「名義人が不明」「未登記」のケースがよくあります。
昔は登記をしていないことも珍しくありませんでした。
親が元気なうちは親族関係や連絡先を確認できますが、認知症になると確認が困難になり、司法書士に依頼せざるを得なくなります。
難しい案件になるほど、費用も時間も大きくかかります。
後見人制度では限界がある
「親が認知症になったら後見人になってリフォームすればいいのでは?」と思う方もいますが、実際はそう簡単ではありません。
後見人制度は「本人の資産を守るための制度」です。
そのため、雨漏れ修繕や維持管理程度は可能ですが、家族の利便性を目的としたリフォームはほとんど認められません。
親が元気なうちにやっておくべきこと
- 将来の住まいについて家族で話し合う
- 不動産の名義や登記を確認する
- 相続や贈与に関する基本知識を持っておく
- 必要であれば司法書士や税理士に相談する
話しにくいテーマですが、後回しにすればするほど解決が難しくなります。
まとめ:リフォームは「親が元気なうちに」が鉄則
ご両親が施設に入ってからリフォームを進めるのは、非常にハードルが高いのが現実です。
認知症や贈与のリスク、親族間の権利関係、名義や登記の問題など、クリアすべき課題は数多くあります。
だからこそ、両親が元気でしっかりしている今のうちに、将来の住まいについて話し合っておくことが大切です。
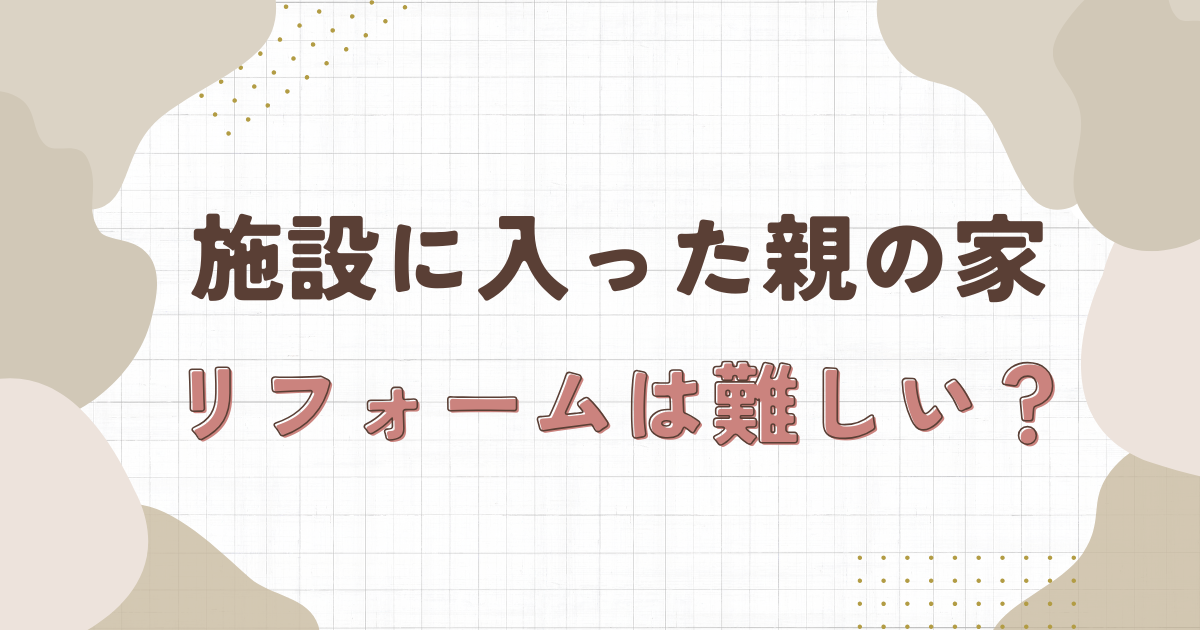

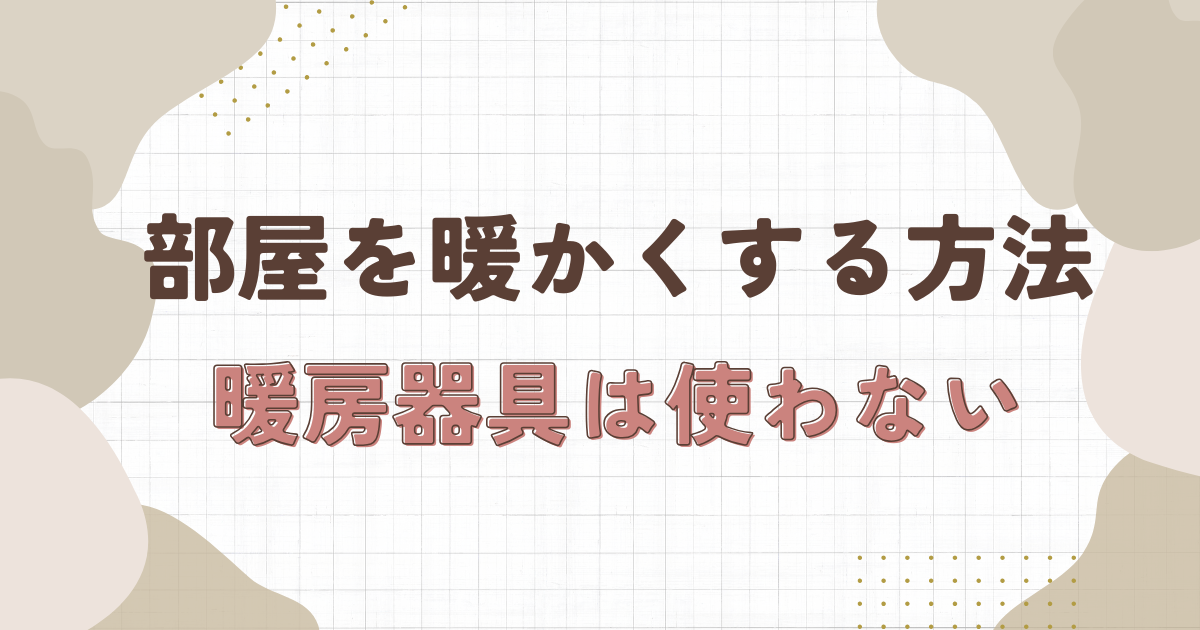
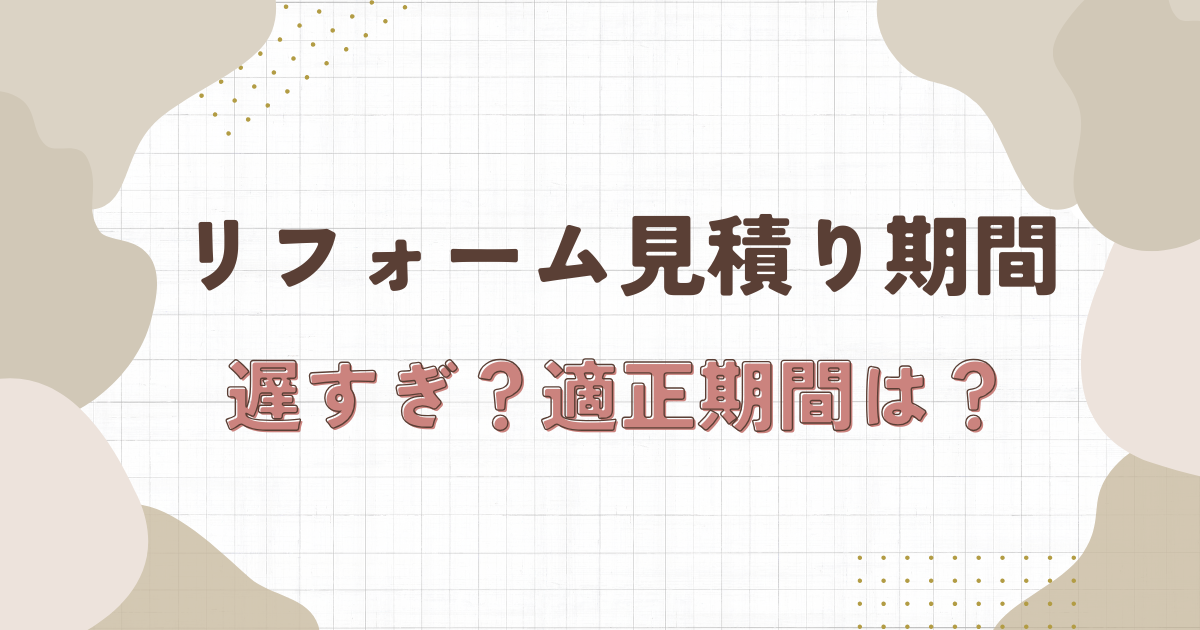
コメント