ーきになるメリットと後悔しやすい落とし穴をプロが解説ー
「ハウスメーカーや工務店を通さず、業者に直接頼んだ方が安くなるんじゃない?」
「知り合いの大工さんにお願いすれば安心でお得では?」
家づくりやリフォームを考え始めると、
“中間マージンを省いた直接発注”がきになる方はとても多いと思います。
確かに、リフォームは決して安い買い物ではありません。
できるだけ無駄な費用を抑えたいと考えるのは、ごく自然なことです。
実際に
「直接頼んだら安く済んだ」
という話を耳にすることもあるでしょう。
しかし、その一方で
「思ったより高くついた」「誰に責任を言えばいいかわからない」
と後悔しているケースも、現場では少なくありません。
この記事では、
リフォームを直接発注した場合のメリットとデメリットを整理しながら、
きになるけれど見落としがちな“落とし穴”について、
元大手ハウスメーカー管理職の視点からわかりやすく解説します。
■この記事でわかること
・リフォームを直接発注すると安く見える理由
・直接発注で抜け落ちやすい重要な役割
・小規模工事なら問題ないケースとは?
・総合的な工事ほどリスクが高くなる理由
・後悔しない依頼先の判断基準
直接依頼=お得とは限りません。
専門的な設計・管理が機能しないと、結果的にコスト増・品質低下・工期遅延といったリスクにつながります。
信頼できるプロに任せることが、遠回りのようで一番の近道です。
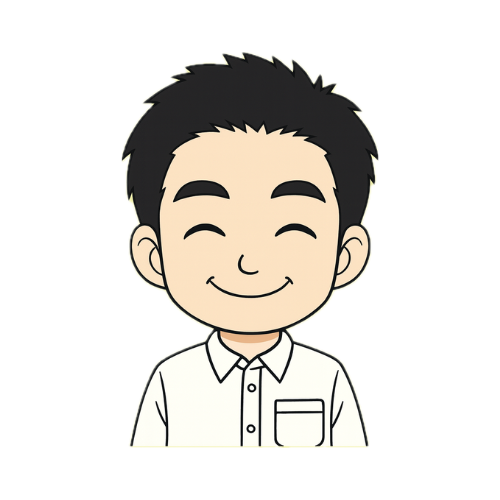
strato
大手ハウスメーカー リフォーム部
元エリアマネージャー
エリア実績 全国No1獲得
現在は独立してブログで住まいの情報発信中
建築業界25年の知識を発信します。
リフォームを直接発注すると安い?きになる理由とよくある誤解

「中間マージンがなくなるなら、その分安くなるはず」
そう考えたことはありませんか?
この考え方、半分は正解で、半分は誤解です。
確かに、営業や管理の費用が減れば、
一時的には金額が下がることもあります。
しかし、
工事が“できる”ことと、“きちんと機能する”ことは別物です。
管理や調整が不足すると、
結果的にやり直しや追加工事が発生し、
「安くするつもりが、かえって高くつく」ことも珍しくありません。
建築は専門家の分業で成り立っている|直接発注で抜け落ちやすい役割
建築やリフォームは、
一人の職人だけで完結するものではありません。
たとえば…
- 要望を整理し、予算と工事内容を調整する営業
- 使い勝手や法規を考える設計
- 現場全体を統括する現場監督
- 工程を調整する設備・電気の管理
- 実際に施工する各専門職人
これらが連携して初めて、トラブルの少ない工事になります。
直接発注では、この中の
「設計」「管理」「調整」が省略される、
もしくは曖昧になりがちです。
その結果、
・誰が判断するのか
・誰が責任を持つのか
が不明確になり、トラブルにつながります。
建築のプロほど直接発注しない理由|ゼネコン監督が外部に頼むワケ
私が大手リフォーム会社に勤務していた頃、
ゼネコンの監督や設計士など、建築のプロからの依頼を多く受けていました。
彼らは「直接やれば安い」ことを十分理解しています。
それでも、あえて外部に依頼します。
なぜか。
それは、
自分の専門外の領域が、全体の品質を左右する
ことを知っているからです。
プロでさえそう判断するのに、
一般の方が個人で全体を管理するのは、
正直かなりのリスクを伴います。

建築の内情をわかっているので
話が通じやすかったです。
段取りと管理が価格を左右する|リフォーム費用はなぜ差が出る?
建築業界では
「段取り八分(はちぶ)」
と言われます。
段取りが良ければ
- 工期は短く
- 無駄な作業は減り
- 品質は安定します
日常的に同じ業務をこなしている人ほど、
結果的に高品質・低コストな工事が可能になります。
逆に、慣れていない管理や調整を行うと、
時間も費用も余計にかかってしまいます。
小規模リフォームなら直接発注もOK?向いている工事・向いていない工事
ここまで読むと、
「じゃあ直接発注は全部ダメなの?」
と思われるかもしれません。
そんなことはありません。
内容が明確な小規模工事なら、直接発注でも問題ないケースがあります。
たとえば…
- 畳の表替え・新調
- コンセントの不具合修理・増設
- エアコンの取り付け・交換
- 水栓金具の交換
- 建具や網戸の調整
これらは
- 工事範囲が限定的
- 他業種との連携がほぼ不要
- 完成形がイメージしやすい
という特徴があります。
このような工事であれば、
信頼できる業者への直接発注でも大きな問題になりにくいでしょう。
最近では便利なサイトもあります。
暮らしマーケット
総合的な工事ほど要注意|リフォーム直接発注のリスクが高まる理由

一方で、次のような工事は要注意です。
- 水回りを複数同時にリフォームする
- 間取り変更を伴う内装工事
- 断熱・耐震・設備更新を含む改修
- 住みながら行う中規模〜大規模リフォーム
これらは
設計・工程・業者間調整が不可欠です。
管理が機能しないと、
- 工期の遅れ
- 手戻り工事
- 追加費用の発生
- 責任の所在不明
といった問題が起こりやすくなります。
【チェックリスト】リフォームを直接発注しても大丈夫?
以下をチェックしてみてください。
□ 工事内容が一つで完結している
□ 他業種との調整が不要
□ 完成形が明確
□ 不具合時の責任範囲がはっきりしている
NOが多い場合は、直接発注は慎重に考えるべきです。

餅は餅屋!
営業にも役割があるんです。
まとめ:リフォーム直接発注には落とし穴がある
リフォームの直接発注が悪いわけではありません。
問題なのは、
工事内容に対して管理体制が合っていないことです。
小さな工事はシンプルに。
総合的な工事ほど、信頼できるプロに任せる。
それが結果的に、
一番安く、後悔しないリフォームにつながる近道です。

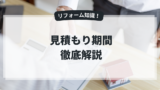

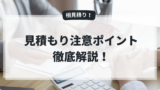

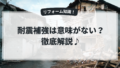
コメント