― 暮らしをラクにする建具サイズと開き勝手の選び方 ―
リフォームを考えると、どうしてもキッチンやお風呂、設備のグレードに目が向きがちです。
でも実は、毎日の暮らしで確実に何度も使う「扉」こそ、住み心地を大きく左右する存在です。
「なんだかこの扉、使いにくい…」
「家具に当たって毎回ストレスになる」
完成後にこう感じる方は、実はとても多いです。
見た目や設備にはこだわったのに、
扉のサイズや開き勝手を“なんとなく”決めてしまった結果、毎日の小さな不便が積み重なる。
これが「扉が使いにくい」と感じる最大の理由です。
この記事では、建築現場で数多くの後悔例を見てきた経験をもとに、
なぜ扉は使いにくくなってしまうのか、
そして後悔しないための建具選びの考え方をわかりやすく解説します。
■この記事でわかること
・扉が使いにくいと感じる主な原因
・生活動線に合った開き勝手の考え方
・引き戸と開き戸、それぞれのメリット・デメリット
・建具サイズを決めるときに見落としがちなポイント
扉は「ただの通路」ではありません。
暮らしを整えるための大切な装置です。
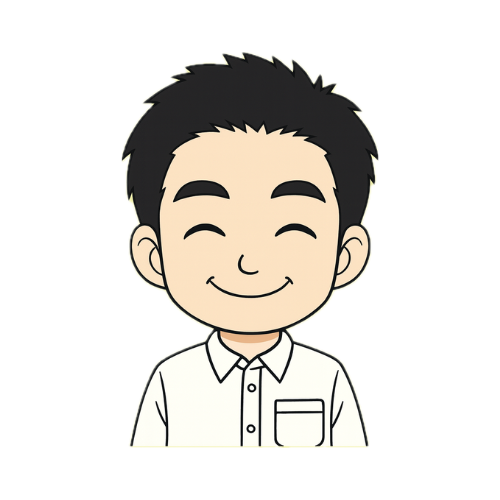
strato
大手ハウスメーカー リフォーム部
元エリアマネージャー
エリア実績 全国No1獲得
現在は独立してブログで住まいの情報発信中
建築業界25年の知識を発信します。
建建具でよくある後悔ポイント

まず、「扉が使いにくい」と感じる代表的な例を見てみましょう。
どれも致命的な欠陥ではありません。
でも、毎日何度も繰り返されることで、確実にストレスになります。
デザイン性も大切ですが、
建具選びで最優先すべきなのは「日々の動線」と「使い方」です。
扉が使いにくいのはなぜ?
結論から言うと、理由はとてもシンプルです。
・生活動線を想定していない
・開き勝手を空間に合わせていない
・サイズを「標準だから」で決めている
この3つが重なると、扉は一気に使いにくくなります。
図面上では問題なく見えても、
実際に人が動き、物を運び、暮らすと違和感が出る。
これが建具の難しさです。
開き勝手はどう選ぶ?
片開きドアを採用する場合、まず確認したいのは
「ドアが開いた先に、十分な余白があるか」です。
たとえば、子ども部屋の扉が狭い廊下側に開くと、
通るたびに体をよけたり、扉を一度閉めたりする必要が出てきます。
基本的には、
部屋に招き入れるように“室内側へ開く”のがセオリーです。
また、
- 吊り元は壁側
- 取っ手は広い空間側
にすると、出入りがスムーズになります。
人は「狭い空間から広い空間に入る」とき、
自然と開放感を感じやすくなります。
ドアの開き方は、心理的な快適さにも大きく影響するのです。

トリックアート迷宮感も視覚を利用して感覚を操作しています。
洗面所・トイレの扉は特に注意
洗面所やトイレなどの狭い空間では、
内開きの扉は基本的におすすめできません。
扉が内側に開くことで、
ただでさえ狭い空間がさらに使いにくくなります。

狭い空間の10cmと広いリビングの10cm
体感は全然違います。
特にトイレでは、
中で人が倒れてしまった場合、
内開きだと外から扉を開けられないというリスクもあります。
そのため、
- 可能なら引き戸
- 難しい場合は中折れ戸
を検討するのが安心です。
扉は「動線」だけでなく「搬入口」
意外と見落とされがちですが、
扉は家具や家電を運び入れるための入口でもあります。
- 洗濯機
- 冷蔵庫
- 介護用ベッド
これらが問題なく通るかどうか、
設計段階で必ず確認しておくことが重要です。
子育て世帯や将来の介護を考えるなら、
作業効率が良く、スペースを有効に使える引き戸は特におすすめです。
引き戸?開き戸?どっちがいい?
結論から言うと、
多くの住宅では引き戸の方が使いやすいケースが多いです。
引き戸のメリット
- 扉の開閉にスペースを取らない
- 空間を一体的に使える
- 動線がシンプルになる
一方でデメリットもあります。
- 開き戸より気密性が劣る
- 価格が高くなることがある
- レール部分の掃除が必要
最近は上吊り式の引き戸もありますが、
その分気密性が下がる場合もあります。
大切なのは、
「どちらが正解か」ではなく「どこに使うか」です。
建具には「造作建具」と「新建材建具」がある
リフォームでよく聞く後悔のひとつに、
「思ったより通路が狭くなった」という声があります。
これは、建具の種類による影響が大きいです。
- 造作建具:柱を活かして作るオーダーメイド
- 新建材建具:メーカー既製品を枠ごと取り付ける建具
新建材建具は、柱の内側に枠を組むため、
同じ位置でも有効寸法が小さくなりやすいのが特徴です。
特にトイレや洗面所などの小さな空間では、
この数センチの差が「使いにくさ」としてはっきり表れます。

この差 結構トラブルの多い項目です(^_^;)
サイズはどう決めればいい?
建具サイズは、
見た目・使い勝手・将来性の3つを意識することが大切です。
一般的な建具サイズは
- 幅:約70cm
- 高さ:約200cm
最近は天井まで伸びるハイドアも人気ですが、
「高ければおしゃれ」というわけではありません。
古い住宅では、
欄間と一体になった低めの建具が美しく機能している例も多くあります。
そこに現代的なハイドアを入れると、
空間全体のバランスが崩れてしまうこともあります。
逆に、建具は200cmで新しく統一したのに、現代的な内装に180cmの建具が残ってしまうと、貧相に見えてしまうことも。
つまり、建具は高さを合わせて“空間に統一感”を持たせることが大切なんです。
幅は「用途」と「動線」が決め手
- 何を通すのか
- 誰が使うのか
- 将来、介護の可能性はあるか
こうした点を事前に考えておかないと、「あれ?これ通らない…」ということも起こります。
さらに、開き勝手は家具の配置や壁掛けテレビの位置によっても変わってきます。
せっかく広いドアをつけても、家具が邪魔して開かない…なんてこともあります。
高さは「空間バランス」で決める
建具の高さは、
床面積・天井高・空間の広がりとセットで考える必要があります。
床面積が小さい空間で建具だけを高くすると、
逆にアンバランスで貧相に見えることもあります。
有名建築家ル・コルビュジエが
黄金比を重視したように、
住まいはバランスがすべてです。
まとめ
扉が使いにくいのはなぜか。
その答えは、設計段階での「想像不足」にあります。
毎日使う扉だからこそ、
「今」だけでなく「これから」の暮らしまで考えて選びましょう。
「ただのドア」から、「暮らしを整えるドア」へ。
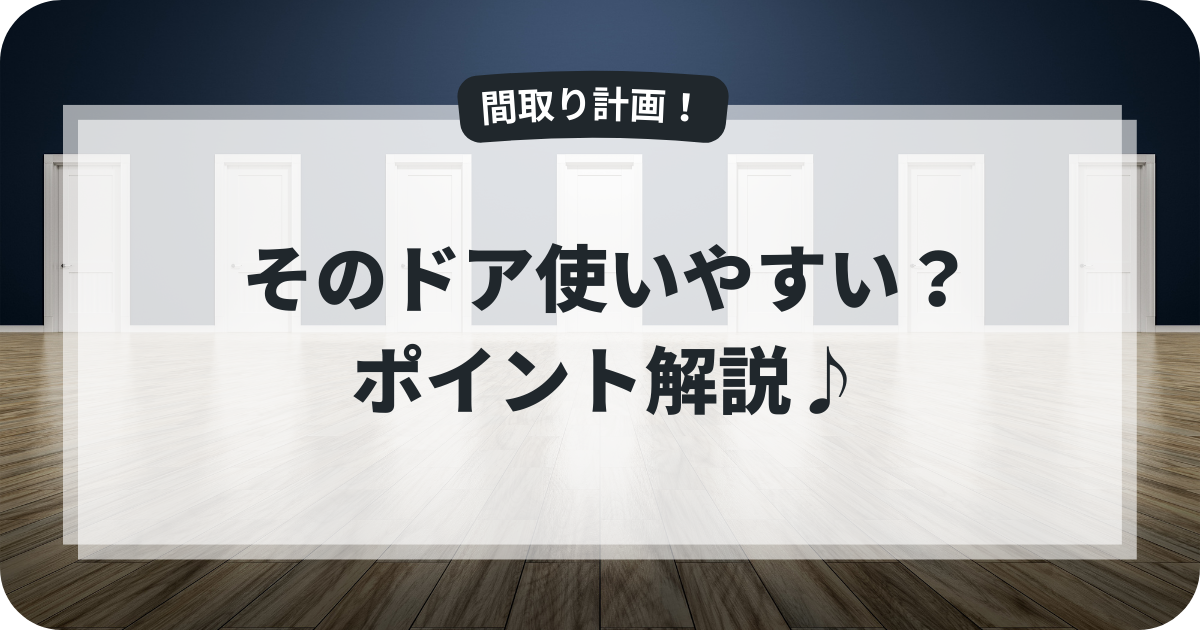
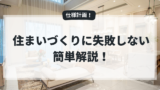
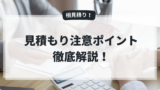
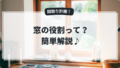
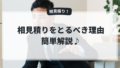
コメント