ープロが教える解消法と失敗しない間取り計画ー
「間取りをどう決めればいいかわからない…」
「プロに任せたはずなのに、住み始めてから不満が出てきた」
「間取りで、こんなにも暮らしやすさが変わるなんて…」
そんな間取りの不満を感じていませんか?
実はその不満、考え方を少し変えるだけで解消できるケースがほとんどです。
間取りは家づくりの“心臓部”ともいえる重要な要素。
にもかかわらず、「なんとなく」「お任せ」で進めてしまい、
住んでから「こんなはずじゃなかった」と後悔する方は少なくありません。
住宅業界で多くの家づくりに携わってきた経験から断言できます。
間取りの不満には必ず原因があり、正しい手順で解消できます。
この記事では、新築・リフォームで後悔しないために
間取りの不満を解消する5つのステップを、実例ベースでわかりやすく解説します。
■この記事でわかること
・間取りの不満を解消するために最初にやるべきこと
・プロが必ず行う「ゾーニング」と不満の関係
・図面だけでは気づけない“使いにくさ”の見抜き方
・365日快適に暮らすための間取りの考え方
・将来の暮らしまで見据えた後悔しない間取り計画
間取り計画は、“自分たちの暮らし”をどれだけ具体的に想像し、設計に反映できるかがカギです。プロ任せにせず、家族みんなで話し合うことが理想の第一歩になります。
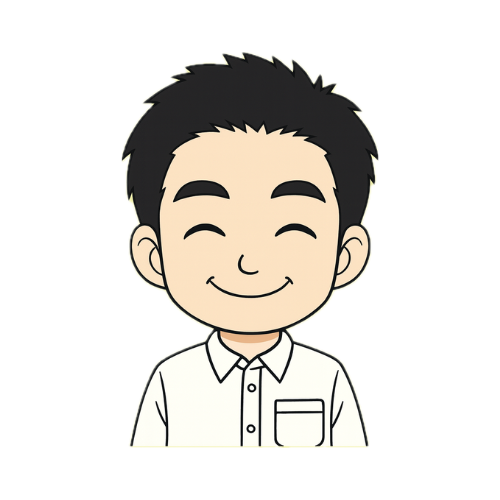
strato
大手ハウスメーカー リフォーム部
元エリアマネージャー
エリア実績 全国No1獲得
現在は独立してブログで住まいの情報発信中
建築業界25年の知識を発信します。
間取りの不満を解消する第一歩|今の暮らしの不便を洗い出す
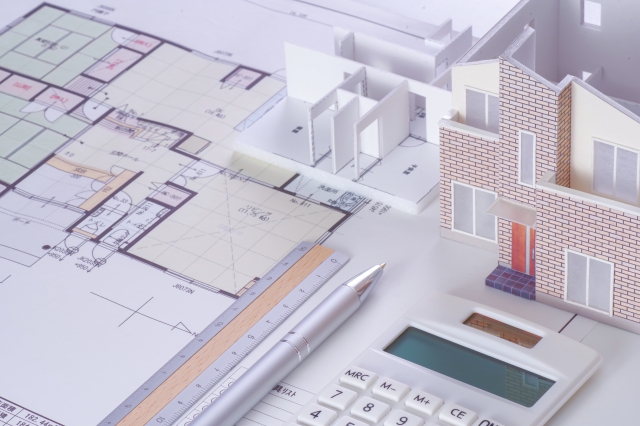
建築雑誌やSNS、住宅展示場には魅力的な間取りアイデアがあふれています。
「これもいい」「あれも便利そう」と、つい目移りしてしまいますよね。
しかし、家庭ごとに生活スタイルはまったく異なります。
流行や見た目よりも大切なのは、
「今の暮らしで何に困っているか」を明確にすることです。
まずは、日常の不満や不便を書き出してみてください。
- 収納が足りず、常に部屋が散らかってしまう
- 玄関が狭く、朝の出入りがストレス
- 高齢の親をサポートしづらい間取り
- 子どもがランドセルを置く場所がない
- ゴミ置き場が丸見えで生活感が出てしまう
こうしたリアルな不満こそが、間取り改善のヒントになります。
設計担当や営業担当には、遠慮せず正直に伝えましょう。
「どんな暮らしをしたいか」ではなく、
「今、何が使いづらいのか」を共有することが重要です。
間取りの不満はゾーニングで決まる|使いにくさを防ぐ配置計画
設計の初期段階で行われるのがゾーニングです。
これは、敷地条件や要望をもとに空間の配置を大まかに決める作業を指します。
- 採光や風通しを考えた居室配置
- 家事動線を意識した水まわり計画
- 収納スペースの確保
この段階では、どうしても一般的で無難なプランになりがちです。
その結果、
「おしゃれだけど使いにくい」
「生活に合っていない」
といった間取りの不満が生まれます。
事前に洗い出した不満を、
ゾーニングにどう反映できるかで、設計者の力量が見えてきます。
設計士の仕事は、
人の力では変えられない自然環境(光・風)と、
社会生活に必要な機能(動線・収納・プライバシー)を
建築設計の技術でつなぐことです。
- プライバシーを守りながら自然を感じる工夫
- プライベートとパブリックスペースの調和
- 暮らしやすさを支える動線と収納計画
なお、ハウスメーカーによっては構造や規格上の制約があり、
思い通りの間取りにならない場合もあります。
その場合は、業者選びを見直すことも大切な判断です。
間取りの不満を防ぐコツ|実際の暮らしを具体的に想像する

次に必ずやってほしいのが、
「その間取りで実際に暮らす自分たちを想像すること」です。
- 朝起きて、どこで着替えるか
- 洗濯物はどこで干して、どこにしまうか
- 子どもが帰宅したら、何をどこに置くか
- 親がデイサービスから帰ってきたら、どこで過ごすか
平面図だけでは、使いにくさは見えてきません。
設計士は空間を立体的に想像するプロですが、
生活の主役は住む人自身です。
家族それぞれが一日の行動を当てはめてみることで、
「ここは不便かも」「ここは助かる」といった
間取りの不満の芽に気づくことができます。
プロの立体的な設計感覚と、
住まい手のリアルな生活イメージが融合して初めて、
便利で美しい住まいが完成します。
プロがあなたに変わって、立体空間世界で思考錯誤します。
間取りの不満が出やすい原因|毎日使う動線を優先する考え方
よくある失敗が、
「たまの特別な日」を優先しすぎてしまうことです。
- 来客が少ないのに立派な客間をつくる
- イベント重視で、普段使わないスペースを確保する
その結果、
毎日使う収納や動線が犠牲になり、
日常に不満がたまる間取りになってしまいます。
大切なのは、
365日使う場所を最優先に考えること。
もちろん、家族の思い出や行事も大切です。
だからこそ、家族で話し合いながら
日常と非日常のバランスを取ることが重要になります。
設計あるあるですが、色々プランを考えて変更していったら
今の住まいと同じになってきた!?

人は現状維持バイヤスにかかりやすいです。
プロの意見を一緒に想像したり 体感してみてください。
将来の間取り不満を解消する|暮らしの変化に対応できる設計
「家は3回建てないと理想にならない」と言われることがありますが、
人生には大きな転換期がいくつかあります。
- 新婚・子育て期
- 親の介護が始まる時期
- 夫婦二人の老後の暮らし
だからこそ、
将来の変化に対応できる間取りが重要です。
間取りに余白や可変性を持たせておくことで、
将来の不満を未然に解消しやすくなります。
どこまで備えても未来を完全に予測することはできませんが、
可能な限り想像し、家族と話し合ってみてください。
間取りの不満を解消する家づくり|後悔しないための考え方まとめ
理想の家づくりは、
強(適切な強度)・用(使いやすさや性能)・美(美しさ)
このバランスがとても重要です。
「かっこいい」と「暮らしやすい」を両立させるためには、
しっかり時間をかけて計画することが欠かせません。
- 今の生活で感じている不満
- 家族それぞれの価値観
- 将来どう暮らしたいか
これらを丁寧に整理し、
家族で生活を想像しながら間取りを考えることが、
不満を解消し、後悔しない家づくりにつながります。
間取りは、暮らしそのもの。
一緒に想像し、一緒に考えることが、
最高の間取りへの第一歩です。

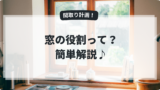
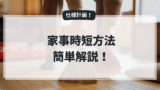
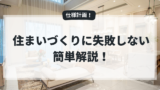
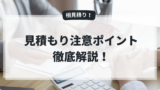

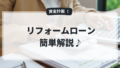
コメント