「実家が築100年以上の古民家だけど、このまま残すべきか、それとも壊して新築にすべきか……」
こんな悩みを抱えている方は、決して少なくありません。
費用はどれくらいかかるのか。耐震性や断熱性は大丈夫なのか。そもそも古民家は、今の暮らしに合うのか。
不安が多すぎて、なかなか一歩を踏み出せない――そんな声を、私自身も現場で何度も聞いてきました。
本記事では、築100年の古民家を「残す」という選択が本当に正しいのかについて、リノベーションの現実・費用感・構造的な特徴を踏まえながら、プロの視点で整理していきます。
この記事でわかること
・築100年の古民家を残すメリット・デメリット
・古民家リノベーションの費用相場と現実
・築100年古民家ならではの構造的特徴
・壊すか残すかを判断するための考え方
築100年の古民家は、ただ古い家ではなく「手に入らない価値」を持つ存在です。
住み継ぐ意志があるなら、リノベーションは“アリ”と断言できます。
ただし、性能向上には費用も手間もかかるため、しっかりと検討と準備が必要です。
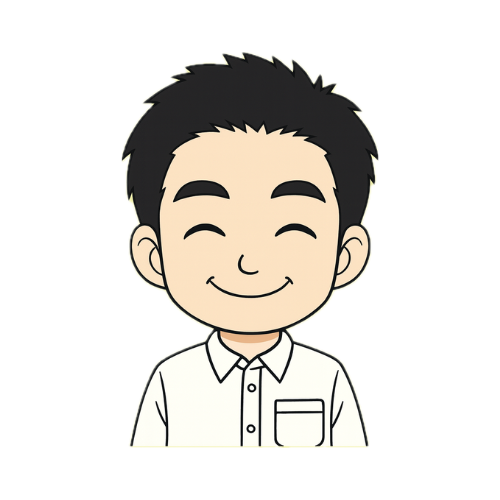
strato
大手ハウスメーカー リフォーム部
元エリアマネージャー
エリア実績 全国No1獲得
現在は独立してブログで住まいの情報発信中
建築業界25年の知識を発信します。
古民家リノベーションは「アリ」なのか?

結論から言うと、住み継ぐ意思があるなら、リノベーションは大いにアリです。
築100年の古民家は、ただ古いだけの家ではありません。
丸太梁や大黒柱、釘をほとんど使わない木組みの構造など、現代では再現が難しい建築技術の集合体です。
一度壊してしまえば、同じものは二度と手に入りません。
この「替えがきかない価値」があるからこそ、「残す」という選択肢が生まれます。
伝統工法の再現は現代ではほぼ不可能
築100年クラスの古民家は、多くが伝統工法で建てられています。
- 丸太梁や大黒柱は、現在では入手困難
- 建築基準法の関係で、再建築できない構法も多い
- 継手・仕口などの大工技術を再現できる職人が限られている
つまり、今ある古民家そのものが希少な資産なのです。

私も古民家再生には特段の思い出があります。
毎回発見と感動があります。
古民家の不満は、だいたいみんな同じ
古民家でよく聞く不満は、ほぼ共通しています。
田の字型の間取りで、北側の暗いスペースが生活空間、南側の日当たりの良い空間は使われない座敷になっているケースも多く見られます。
高い床下は通気性こそ良いものの、断熱材が入っていない住宅がほとんどです。
そのため、現代の暮らしに合わせるには、部分的な改修では済まず、大規模なリノベーションが必要になることも少なくありません。
住んでから気づく、古民家ならではの価値
一方で、古民家には新築住宅では得がたい魅力もあります。
- 縁側や広縁からの借景の美しさ
- 深い軒がつくる夏の涼しさ
- 無垢材や大黒柱の圧倒的な存在感
- 左官仕上げに残る職人の手仕事
これらは、新築住宅ではなかなか得られない価値です。
「壊してから、その良さに気づいた」という声も、決して珍しくありません。
古民家リノベーションのデメリットと現実
デメリット① 費用が高い
古民家リノベーションは、一般的な住宅リフォームより1.5〜2倍以上かかることもあります。
| 工事内容 | 費用目安 |
|---|---|
| 屋根(和瓦葺き替え) | 1000万円以上 |
| 外壁(漆喰+焼杉板など) | 500万円〜 |
| 内部リノベ(断熱+意匠残し) | 坪単価50万円〜 |
| フルリノベ(50坪) | 2500万円〜3500万円程度 |
※条件・地域・会社によって差があります
外観の雰囲気を守るため、和瓦・漆喰・焼杉板などの伝統素材を使う場合、どうしてもコストは上がります。
一方で、ガルバリウム鋼板やサイディング材、杉板張りなどを取り入れ、現代的にアレンジする選択肢も可能です。
また、すべてを一度にリノベーションするのではなく、「まずは水回りだけ」「屋根だけ葺き替える」など段階的に進める方法もあります。費用を抑えたい場合や、予算の都合がある場合におすすめで
デメリット② 構造・性能の課題
- 耐震・断熱性能の向上が必須
- 維持管理の手間がかかる
- 対応できる業者が限られる
古民家を熟知した業者に頼まないと、後々コストがかかることもあります。
築100年の古民家構造とは?

築100年以上経った古民家は、いわゆる伝統工法で建てられた住宅です。
現代のようなコンクリート基礎ではなく、敷石や束石の上に柱を立てる構造が特徴で、柱や梁は木組みによってつながれ、釘をほとんど使わずに構成されています。
この時代の住宅には、大黒柱・中黒柱・小黒柱といった存在感のある構造材が使われ、それらを「牛木(うしぎ)」と呼ばれる丸太梁で結び、建物全体を支えています。
見上げれば、圧巻の梁組が頭上に広がり、先人たちの職人技を直に感じることができます。
また、壁が少なく、襖や障子で空間を仕切るため、暮らしに合わせて大空間をつくれる柔軟さも特徴です。
高い床下と深い軒の出は、湿気対策・日除け・通風を自然の力でまかなう、理にかなった造りと言えるでしょう。
一方で、敷居と鴨居の高さが約1730mm前後と、現代人には低く感じられる場合もあります。これが「住みにくさ」と感じる原因のひとつです。
構造に配慮しながら高さ調整を行うことで、現代のライフスタイルに適応させることも可能です。
屋根には和瓦が載り、その下には大量の土が敷かれています。この重みで建物を安定させるという考え方で、地震時には瓦が落ちることで力を逃がす構造でもあります。
やじろべえ現象や、土壁の粘り、仕口の柔軟性など、伝統工法は地震の力を受け流す思想でつくられています。
ただし、現代の耐震基準で数値化すると不利な評価が出やすいのも事実です。そのため、現在は一般的な耐震補強を併用するケースが多くなっています。
リフォームのタイミングは「世代交代」
古民家リノベーションの多くは、親世代から子世代への住まいの引き継ぎがきっかけです。
これらを家族でしっかり話し合うことが、後悔しない選択につながります。
なお、古民家が市場に出るケースの多くは、受け継ぐ子や孫がいなくなったタイミングでもあります。
信頼できる業者選びが、結果を左右する
古民家リノベーションは、業者選びがすべてと言っても過言ではありません。
伝統工法を理解していない会社に依頼すると、貴重な古材を失ったり、構造的に危険な施工になることもあります。
過去の施工事例を確認したり、実際に現場を見せてもらったりすることで、信頼できるパートナーかどうかを判断しましょう。
築100年の古民家は残すべき?判断チェックリスト
ここまで読んでも、「自分の場合はどうだろう?」と迷っている方も多いはずです。
そこで、古民家を残すか・壊すかを判断するためのチェックリストを用意しました。
古民家を「残す」選択が向いている人
古民家を「壊す」選択が向いている人
このチェックで「残す」に多く当てはまるなら、
築100年の古民家リノベーションは前向きに検討する価値があります。
失敗しないために、まずやるべきこと
古民家リノベーションで後悔するケースの多くは、
最初の判断と業者選びでつまずいています。
いきなり工事の話を進めるのではなく、まずは次のステップがおすすめです。
- 建物の現状をプロに見てもらう(構造・劣化・傾き)
- どこまで性能を上げたいかを整理する
- 「残す部分」と「変える部分」を家族で共有する
- 古民家の実績がある業者に、複数の考え方を聞く
この段階を丁寧に踏むだけで、失敗の確率は大きく下がります。
まとめ:築100年の古民家を残すという選択
築100年の古民家は、ただの古い家ではありません。
そこには、家族の歴史と、日本の住文化が詰まっています。
もちろん、リノベーションには費用も手間もかかります。
それでも「残したい」と思えるなら、その価値は十分にあります。
壊せば、もう二度と戻らない。
だからこそ、家族とよく話し合い、信頼できるパートナーとともに、
次の世代へ住まいをつないでいく選択をしてほしいと思います。

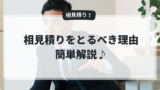
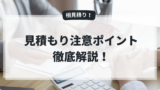
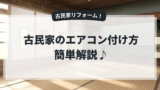
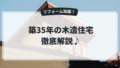
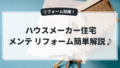
コメント