ー相続した家は住む?売る?建築のプロが判断基準を解説ー
「親から家を相続したけれど、どうすればいいのかわからない」
「住むには古い気がする。でも手放すのも気が引ける」
「建物が古いけど、修繕して使えるの?放置したらどうなるの?」
そんな相続住宅に関する不安や迷いを抱えていませんか?
実際、多くの方が“実家の建物状態が分からない不安”を抱えています

親が健在な時には、なかなか話しにくい内容ですよね。
事前に知識を入れて早めの相談がベストです。
相続住宅の最適な選択肢は、建物の状態・構造・立地・今後のライフスタイルによって異なります。だからこそ、冷静かつ現実的に「判断材料」を揃えることが、後悔しないための第一歩です。
この記事では、相続した家について、感情だけではなく「建築的な視点」から判断できるようになります。結果として、将来的なトラブルや無駄な出費を避け、家族にとって最適な選択ができるようになるはずです。
■この記事でわかること
・相続住宅を「住む」「売る」「貸す」といった選択肢の違い
・木造・鉄骨・RC造など構造ごとの寿命と注意点
・建て替え・リフォーム・売却、それぞれのメリット・デメリット
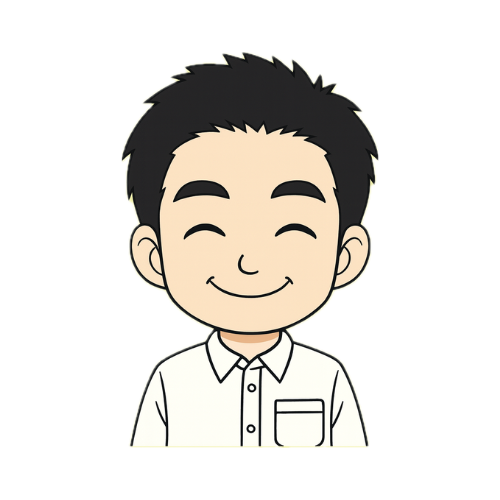
strato
大手ハウスメーカー リフォーム部
元エリアマネージャー
エリア実績 全国No1獲得
現在は独立してブログで住まいの情報発信中
建築業界25年の知識を発信します。
相続後の選択肢|住み替え?売却?賃貸?
「結局どうするのが正解なの?」
この問いに絶対的な正解はありませんが、判断の軸として重要なのは、
- 建物の劣化状態
- 構想(木造・鉄骨造など)
- 今後の修繕・維持コスト
- 立地条件
このバランスです。
建築の視点から言うと、「建物のメンテナンス状況と劣化度合い」が最も大きな判断材料になります。
ただ不動産である以上、「立地条件と価格バランスが非常に重要」です。立地条件によっては価格がつかないこともあるので、その点はご注意ください。
放置しておくと近隣からの問い合わせや、建物のイラズラ、空き家に対する行政指導リスクもあります。
構造別に見る建物の寿命と注意点
木造住宅
柱や梁、土台などの主要構造部が木でできている建物は、
しっかり乾燥状態が保たれていれば100年以上もちます。
日本の気候にも適していて、良い素材です。
ただし、「雨漏り」や「シロアリによる被害」などの欠損がある場合は補修が必要です。
補強がしやすい構造ではありますが、内部構造から施工が必要なため費用は多くかかります。
耐震性については、基本的に西暦2000年以前の建物は耐震補強が必要と考えてください。
ハウスメーカーの家などは、自社で補強計画をしていることもあるため一概には言えませんが、
長く住む予定がある場合は耐震診断は必須です。
また、木造にも種類があります。
ハウスメーカーの**木質パネル構造(規格住宅)**は、補強が困難です。
とはいえ、さすがはハウスメーカー!調査してみると数十年経った家でも、非常にしっかり建っている印象を受けます。
間取りに不満がなければ、メンテナンスだけで住める・貸せることも多いです。
ただし、基礎部分に傷みがあると、爆裂現象や風化が進んでいる場合、正直、手放す判断をすべき家もあります。
(RC造で後述します)
木造部分だけを補強し、基礎に負担がかからないようにバランスをとることも可能ですが、限界はあります。
S造(鉄骨造)
重量鉄骨・軽量鉄骨で組まれている建物です。
錆びていなければ、当初の強度はキープされていると考えられます。
ただし、雨漏りが致命傷になります。鉄が錆びると補強が非常に困難です。
特に**ハウスメーカーの軽量鉄骨(規格住宅)**は、建てた会社でなければ補修できせん。
規格住宅なため、そもそも直せるかどうかも不透明です。
耐震性に関しては、2階建て程度の一般住宅が倒壊する可能性は低いと考えられます。
間取りの自由度は軽量鉄骨と重量鉄骨によって異なります。
重量鉄骨のラーメン構造(柱と梁で支える)は、比較的自由が利きます。
ただし、**耐火被覆材にアスベスト(石綿)**が含まれている場合、除去に1000万円以上かかることもあり、触ることすらできない可能性もあります。
都市計画区域(駅近くなど)の防火地域のS造は要注意です。アスベストは所有者責任で除去が必要です。

知らない間に 大きな負債の相続になってしまいます。
親が健在な時にしっかり調査確認することをオススメします。
RC造(鉄筋コンクリート造)
鉄筋とコンクリートで構成される住宅で、
コストが高いため「お金持ちの家」という印象があります。
その分、重厚感・自由な形状・大空間を実現できます。
しかし雨漏りによる「爆裂現象」は致命的
耐久性はあるが、酸化とともに内部破壊が進行
補修は専門業者でないと困難。費用対効果が見込めない
維持には防水・塗装の定期メンテが絶対条件です。
メンテナンスされていないRC造は、手放すことを検討した方がいい場合が多いです。
木造よりも解体費用はかかりますが、将来の維持費を考えると補修の繰り返しは費用対効果が見込めません。

40年以上塗装メンテナンしていないと
長く住むのは難しいでしょう。
マンション・集合住宅
管理会社がしっかりしていれば、基本的に問題ありません。
管理費・修繕積立金を活用して、適切なメンテナンスが行われているはずです。
区分所有の場合は、立地や今の家族構成に合っているかどうかで住むか貸すかを判断できるでしょう。
ただし、「空き家が多い」「滞納世帯が多い」場合は要注意。
管理組合への確認をおすすめします。
住民の高齢化が進むと、駐車場の利用状況も積立金に影響します。豆知識として抑えておきましょう。

修繕計画がしっかりしていると安心です。
大相続時代
日本の空き家数は、2023年時点で約900万戸に達しました。(※総務省調査より)
特に団塊世代の高齢化が進む中、今後も空き家は増え続ける見通しです。
私が勤務していた当時も、年々「家の相続」に関する相談が増えていました。
「住み替えようか悩んでいます」
「親が高齢なので今のうちに準備したい」
「この家、住むか手放すか迷っています」など
相続された家が、負の遺産にならないように、早めの判断と準備が大切です。
建て替え?リフォーム?どっちがいい?
建て替え or リフォームの判断基準は以下の通り。
| 比較項目 | リフォーム | 建て替え |
| 費用 | 安く抑えられることも | 高額になりがち |
| 工期 | 短く済む場合も多い | 時間がかかる |
| 自由度 | 制限あり | 自由に設計可能 |
| 固定資産税 | 安く済む場合も | 増額の可能性あり |
住むにしても、貸すにしても間取りのニーズ(ファミリー層か新婚層)、構造の安全性、今後のメンテナンス費用、このバランスを考慮して判断することが重要です。
木造なら補強や間取り変更がしやすいですが、他の構造は現状の間取りを活かすことになります。
正直、調査してみると建て替えが必要な家も多くあります。立地条件が合わなければ手放す方が負担が少なく済むことも多いです。
思い出が詰まった家だからこそ判断が難しいこともありますが、冷静な判断が大切です。
また、貸す場合にも貸主としての責任が発生します。
「自分が住むなら許容できる状態か?」を最低基準とし、
お持ちの間取りの需要がある地域かどうか?
メンテナンスと利回りのバランスは取れているか?を含めて専門家に相談することをおすすめします。
まとめ|家族の未来のために「今」決めておくこと
相続物件は、思い出の詰まった大切な場所でもあり、
一方で大きな責任やコストがのしかかる存在でもあります。
- 今の建物が安全に使える状態か
- 維持費や修繕コストはどのくらいかかるか
- ライフスタイルあっているか
これらを冷静に見極めたうえで、
「残すのか、手放すのか、建て直すのか」選択していきましょう。
放置しても問題の解決にはなりません。
自分たちの代でしっかりと判断しておけば、次の世代にも負担を残さずに済みます。
少しでも参考になれば幸いです。
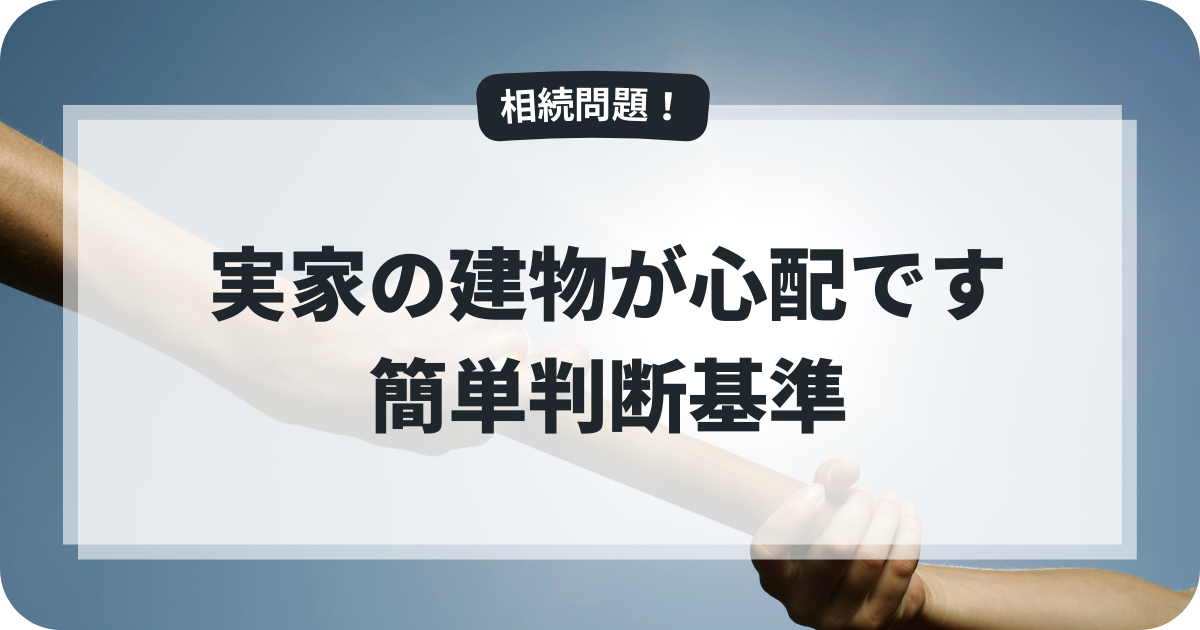
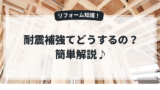
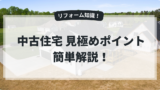
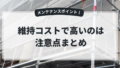
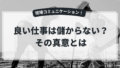
コメント